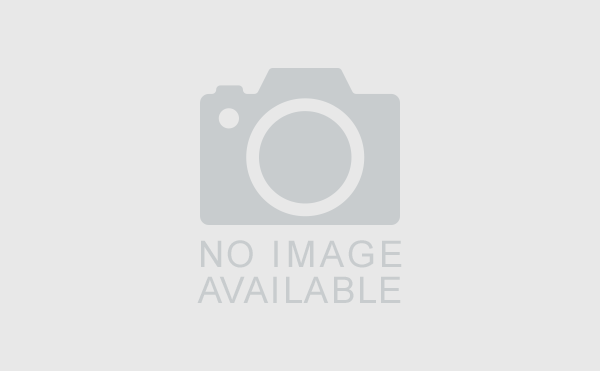上越地域現地見学会
日時:2025年10月12日(日) 10:00~17:00
見学場所:高田特別地域気象観測所、地すべり資料館、雪崩資料館、雪崩対策施設など
参加者は直江津駅北口前に集合し、2台の車(1台はレンタカー)に分乗して以下のルートで回りました。
・高田特別地域気象観測所(上越市大手町)
旧高田測候所が2007年(平成19年)に自動観測システムへの移行により無人化され「高田特別地域観測所」になりました。現在は気温、降水量、風向風速、日照時間、積雪深、湿度、気圧を観測、全国33地点のウインドプロファイラ観測局の一つでもあります。
見学では、露場の近くまで歩いて行くことができ、気象観測装置の設置状況やウインドプロファイラ施設を遠目で見学しました。
・高田城址公園(おまけ)
高田特別地域気象観測所にほど近い、夜桜や蓮で有名な高田城址公園を移動中の車の中から見学しました。
・地すべり資料館(上越市板倉区猿供養寺)
新潟県上越地方は、地質的に新しく柔らかい新第三紀層が広く分布し、雪解けの期間が長いことから、日本一の地すべり多発地帯と言われており、この地域の人々は古くから地すべりの被害に悩まされてきました。当資料館は日本で最初にできた地すべりの資料館で、映像メディアや模型などがあり、「地すべり」を中心に小学生や一般の方々が自然災害と防災について、分かりやすく学習できるよう展示されています。また、屋外には地すべりを鎮めるための人柱で全国的に有名な人柱供養堂も併設されています。
見学では、時間の関係でDVDシアターなどは残念ながらパスし、パネル展示を中心に見学し、地すべりをはじめとする自然災害について学ぶことができました。
・道の駅マリンドリーム能生(糸魚川市能生)
横綱大の里の出身高校である海洋高校が近くにあり、道の駅入口にも等身大のパネルが設置されています。三連休の中日ということもあり大変な混雑のなか、ここで昼食休憩をとりました。
・雪崩資料館(糸魚川市田麦平)
昭和61年(1986年)1月26日、能生町(現糸魚川市)柵口の権現岳中腹から発生した雪崩により13名の方が亡くなる雪崩災害が発生しました。来年の1月で災害から40年を迎えます。この資料館では、雪崩が起こる仕組みやいろいろな対策施設を学習することができるよう、模型やパネル等が展示されています。
見学では、雪崩が発生した時の気象状況、雪崩の経路やその対策として設置された対策施設等について、ジオラマやパネルなどにより理解を深めることができました。
・雪崩対策施設(糸魚川市柵口)
柵口には災害発生後数年をかけて日本最大級の各種雪崩対策施設が設置されています。
見学では、実際に設置場所まで移動して減勢工と防護工を間近で見学し、施設の大きさを実感しました。午後から雨の予報でしたが、最後まで雨に降られずに見学会を終えることができました。
その後、直江津駅まで戻りレンタカーを返却した後、17時過ぎから駅前の居酒屋で懇親会を行いました。参加者は8名中6名、約2時間いろんな話題で親交を深めることができました。
今回の現地見学会参加会員は、阿部祐一会員・池川泰介会員・大原栄亮会員・高澤寛会員・水科進会員・水野敏明会員・渡辺伸一会員(以上新潟支部)、高木育生会員(神奈川支部)の8名です。