かながわ労働プラザ 第3会議室:対面とオンラインの併用(ハイブリッド)形式
内容
招待講演
横浜地方気象台長 杵渕(きねぶち)健一様

予報業務の変遷について
平成26(2014)年8月の広島土砂災害は、今後の予報業務を考える重要なきっかけになり、「新たなステージ」に対応した防災気象情報と観測・予測技術のあり方を検討することになった。
また、平成30(2018)年7月豪雨に対しては、<目指すべき社会>として、住民は 「自らの命は自ら守る」意識を、行政は住民が判断できるよう全力で支援することが提言され、その実現のため防災情報を 5段階の警戒レベルにより提供し、受け手が情報の意味を直感的に理解できるような取組を推進することにした。
現在、気象庁では2030年の科学技術を見据えた気象業務のあり方についても検討を行っており、自然災害の頻発や気候変動に対して先端AI技術の適用などを検討している。
将来の予報作業については、予報官の監視・判断・行動の時間を増やすため、予報業務体制を見直し地台予報官を作業から解放することや、現YSS(予報作業支援システム)の高度化等を検討している。
気象予報士会会員発表
島田賀子 会員
虹は何色?
いつから虹は7色になったのか? 浮世絵では、虹は3~4色だったが、江戸時代末期(1825年)オランダ語を訳した日本で最初の物理科学書で、「虹は7色」と紹介され、それ以来、虹の色は7色となった。これは、ニュートンが「虹は7色」と言ったことがオランダに広まり、日本に伝わったためと考えられる。
その後、7色を見分けるのにはそもそも無理があるとして、アメリカやイギリスでは7色から6色に変更されている。日本でも「理科年表」では「虹は6色」とされている。そのうち日本でも「虹は6色」となるかも?
ちなみに世界的には、7色/6色/5色/4色などの国がある。
長嶋賢一 会員
日本一の梅の産地、和歌山県のみなべ町訪問しての梅の開花考察
南高梅の産地である和歌山県みなべ町を訪問したので梅の開花について考察した。
梅は桜に比べて休眠が浅く、冬の天候の影響をダイレクトに受ける(冬の高温→開花促進、冬の低温→開花遅れ)。厳冬の年は、梅の開花日が遅れ、桜の開花日との間隔が短くなる。緯度/標高が高くなるにつれ、梅の開花日が遅くなり、桜の開花日に近づく。その結果、桜前線(そめいよしの)は1か月強で日本を縦断するが、梅前線は3か月以上、年によっては4か月以上を要する。
梅の開花日を予測することは大変難しい。梅という貴重な観光資源をより有効に活用するためにも、精緻な季節予報および開花予想が望まれる。
濱野哲二 会員
シリーズ日露戦争と気象③ 黒溝台(こっこうだい)会戦~もう一つの八甲田山
有名な八甲田山雪中行軍遭難事件の母体は東北の第八師団であった。その第八師団が、日露戦争での酷寒の戦場に投入されることになる。「黒溝台会戦」である。
八甲田の遭難の悲劇とその教訓、研究成果は、日本陸軍の冬季装備にそれなりに生かされたものの、未だ試行錯誤の段階であり、黒溝台会戦では、第八師団が雪原の上で文字通りの凄惨な苦戦を展開し、ロシア軍は突如後退、日本軍の全戦線崩壊はかろうじて免れることができた。
この第八師団の酷寒下での激闘は、彼らにとっての南満州の戦場に表出した「もう一つの八甲田山」であったと言えるのではないだろうか。(発表者記)
吉田憲司 会員
「てんき」から「でんき」へ ~身近な電磁気現象に触れてみよう~
電力設備の保安監督に必置な電気主任技術者制度を紹介されたあと、雷でもおなじみの電気について、豆電球の回路や静電気現象を出発点に解説がなされた。
アンペールの法則、フレミング右手則・左手則、電磁誘導などの電磁気の諸法則を図解で示し電気現象と磁気現象が密接につながっていることが解説され、そのあと、直流電動機や誘導電動機の動作原理と、その速度、トルク制御に使われるサイリスタチョッパ制御、界磁添加励磁制御、VVVFインバータ制御説明された。
その実例としてこれらが使われている電鉄車両の特徴と、電車が発する走行音(チョッパに使われるサイリスタやインバータなどの動作音)を紹介され、参加者は電車の走行音が電磁気現象の宝庫であることを実感した。電車に搭載されるインバータについて、メーカーにより動作音に特徴があることが良く分かった。
集合写真
参加者数 対面参加者:39名、オンライン参加者:21名、計60名(講師含む)
懇親会(横浜中華街・鳳林):35名
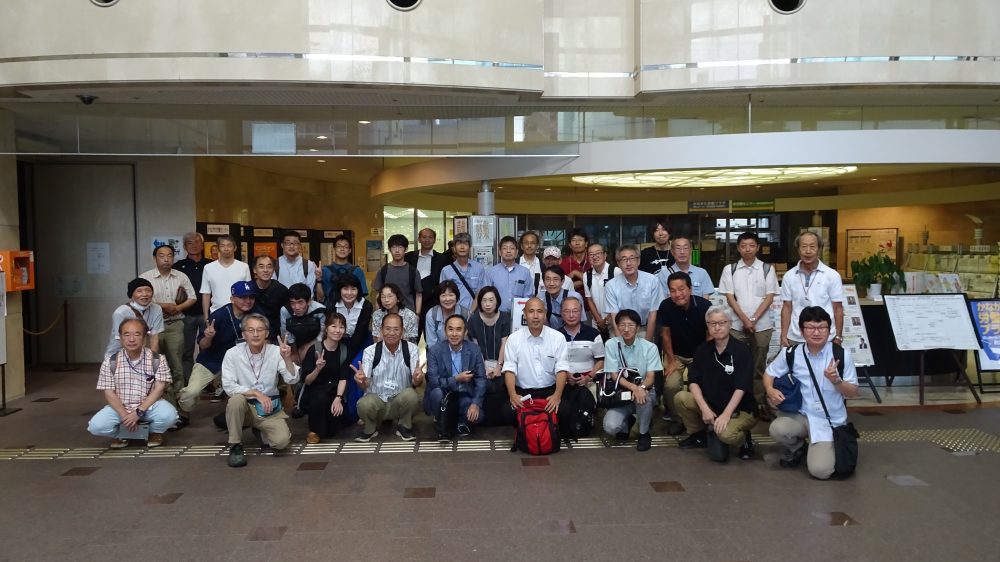
.jpg)




